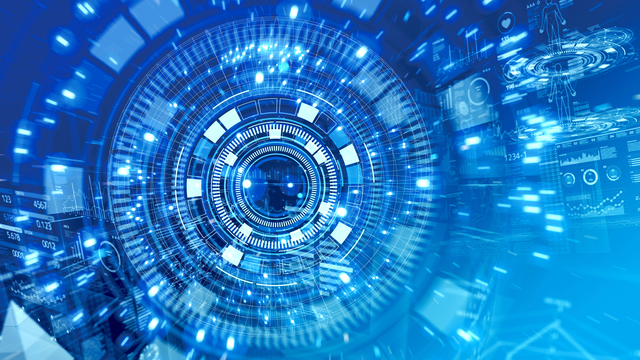トライバンドとは?デュアルバンド、シングルバンドとの違いも
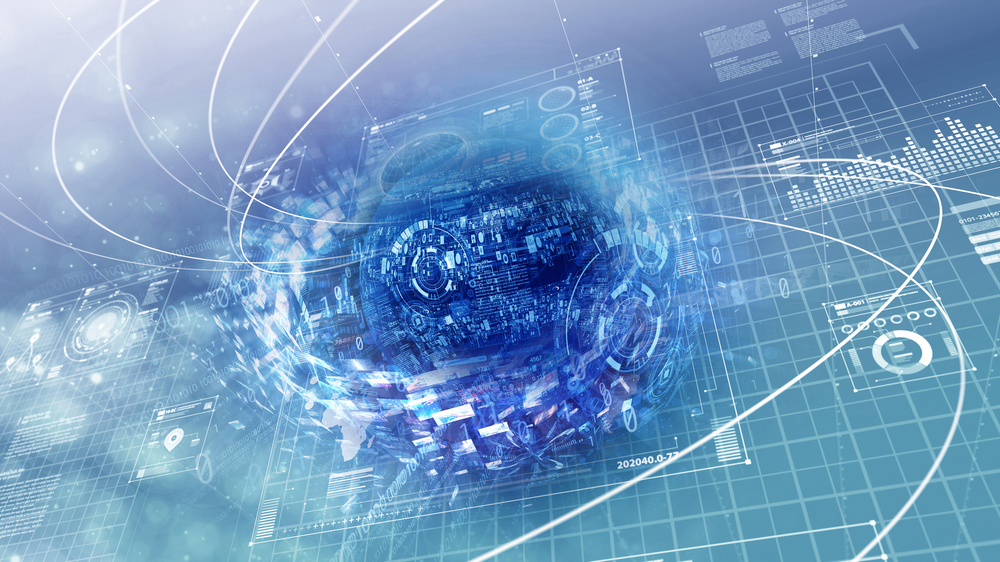
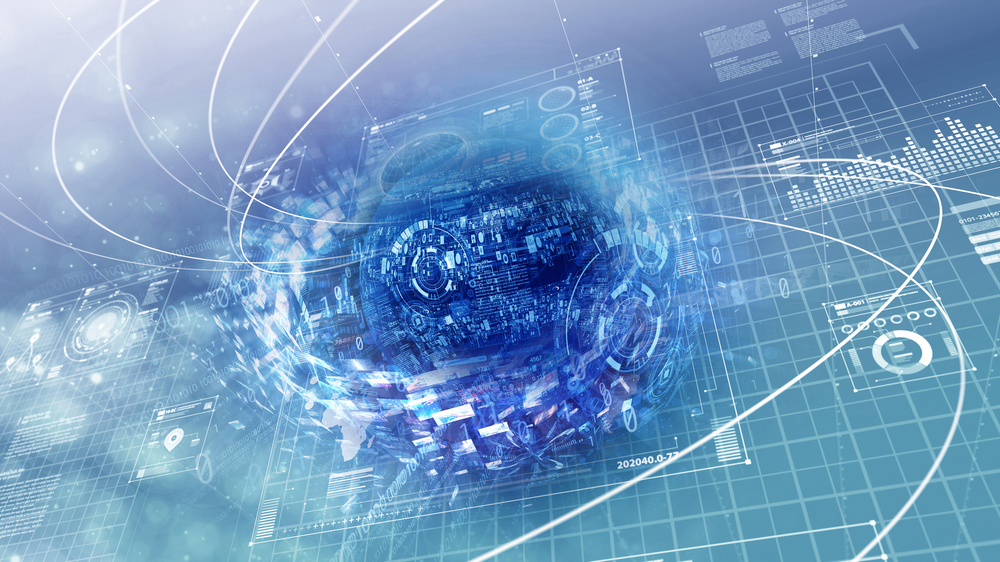
トライバンドとは「3つの帯域」という意味で、その名の通り通信機器が「3つの周波数帯域での通信」に対応しているということです。
これまでは「デュアルバンド」と呼ばれる2.4GHzと5GHzの2つの帯域を使って無線LAN通信を行う方法が一般的でした。
デュアルバンド通信では、ネットワーク速度が急に低下したり、Wi-Fi接続が障害物に遮られたりすると、中断したりと、不満も多くありました。
そこで登場したのがトライバンドです。トライバンドは、2.4GHz帯に加え、5GHz帯(W52・W53)、5GHz帯(W56)という2つの5GHz帯に対応したアンテナを備えたWi-Fiルーター(アクセスポイント)を使って、合計3つの帯域を使って通信を行う方法です。
これにより、2.4GHz帯、5GHz帯それぞれが持つメリットを享受できるため、通信速度が早く、障害物に強い、負荷を分散させて競合や混雑を抑制することで快適な通信が可能になります。
デュアルバンド、シングルバンドとの違い
デュアルバンドという仕様が出てきましたが、パソコンの無線LANにはこれ以前に、「シングルバンド」という仕様があります。
シングルバンドは2.4GHz帯と5GHz帯の2つの帯域を交互に使用し、1つの帯域のみ中継する方式で、無線LANの周波数帯はここから始まりました。
2.4GHz帯は遠くまで電波が飛ぶ、障害物に強い、電波干渉が多い、通信速度が遅いといった特徴があり、5GHz帯には電波干渉が少ない、通信速度が速い、電波が遠くまで飛ばない、障害物に弱いといった特徴を持っています。
シングルバンド対応のルーターは、通信時、同じ周波数帯にする必要があるため、ルーター本体で切り替えを行わなければならず、通信処理に倍の時間がかかり、通信速度が半減してしまいます。
一方デュアルバンドで通信する場合は、2.4GHz帯と5GHz帯の2帯域を同時に利用することができます。
例えば、親機と中継器の通信は5GHz帯で通信を行い、中継器と子機の通信は、もう一方の帯域の2.4GHz帯で通信します。
同じ周波数帯では送信と受信が同時にできないため、ルーター親機と通信中は子機と通信ができませんが、2.4GHz帯と5GHz帯であれば、本体の中にあるフィルタで分けることができるため、2.4GHz帯で親機と通信中に、5GHz帯で子機と同時に通信を行うことが可能です。
それらに対しデュアルバンドの2.4GHzと5.0GHzにくわえ、もう一つ別の5.0GHz帯の電波も使えるようになっているのです。
3種類の電波を同時に使うため、ルーターの脳的な役割である「CPU」も、デュアルバンドより多く搭載することで強化しています。
トライバンドのメリット
2.4GHz帯と5.0GHz帯の特徴をそれぞれまとめると、2.4GHz帯の場合は速度は遅いが、障害物に強い、5.0GHz帯は速度は早いが、障害物に弱いといったことがいえます。
つまり、シングルバンドやデュアルバンドではこういったそれぞれのメリットを活かしたり、デメリットをカバーするような使い方はできなかったのですが、トライバンド対応の機器を使用することで、可能になったわけです。
速いスピードと安定した接続を求めるなら、トライバンドがおすすめです。
また、大きなメリットの1つとして、Wi-Fiの接続台数が多くても安定した通信を供給できる、という部分があります。
特にオフィスで多くの人が同時に接続したり、家庭でも家族全員でそれぞれが持つパソコンやスマートフォンで端末高画質動画を見る場合などでも、快適に通信を維持することが可能になります。
例えばハイエンド機種「TP-Link Archer C5400」であれば最大64台まで同時接続で快適な通信をすることができるといわれています。
トライバンドのデメリット
トライバンドについては「デメリット」といえるデメリットは無いといえるのですが、使用する方によってはおすすめできない、というケースもあります。
例えば、一人暮らしで家でインターネット接続をする場合などであれば、同時にWi-Fiデバイスを何台も接続することはあまりないと思われますので、そういった場合はデュアルバンドルーターで間に合うと思います。
また、あまり高画質の動画は見ない、容量が思いファイルを取り扱ったりすることがない方にとっては、トライバンドはコスパ的によくないケースもあると思います。
ただ、最近ではトライバンドルーターでもかなり安い製品も次々に発売されてきていますので、いずれにしても通信速度は速いに越したことはないと思いますので、コスト的に問題にのであれば、トライバンドルーターを一度検討してみてはいかがでしょうか。